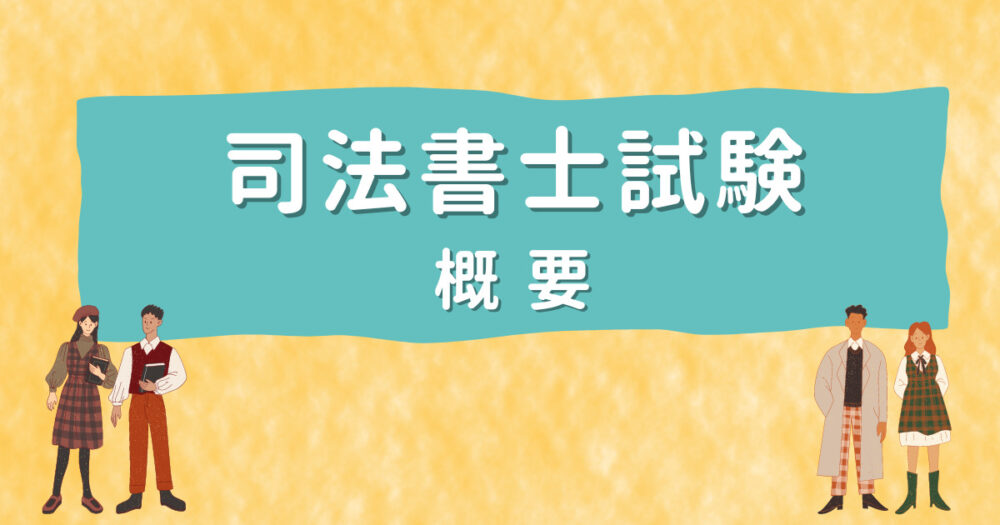司法書士一次試験の内容
試験当日のスケジュール
※司法書士試験じたいは、午前の部が09:30からスタートしますが、09:00には、受験番号で指定された席についてなければなりませんので、注意が必要です。
| 午前の部 09:30~11:30 |
【択一式】 ・憲法 3問 |
計35問 (105点) |
| 午後の部 13:00~16:00 |
【択一式】 ・民事訴訟法 5問 |
計35問 (105点) |
| 【記述式】・不動産登記法 1問 問36 | 計2問 (70点) |
|
| 【記述式】・商業登記法 1問 問37 |
概括
| 午前の部 (9:30~11:30) |
択一式 35問 | 2時間 |
| 午後の部 (13:00~16:00) |
択一式 35問 | 3時間 |
| 記述式 (不動産登記法) 1問 | ||
| 記述式 (商業登記法) 1問 |
司法書士試験合格までのながれ
***PR・広告***
1年間のスケジュール
⇒出願方法 : 受験希望地の法務局・地方法務局に、郵送または持参
⇒受験料 : 8,000円(収入印紙を願書に貼る)
⇒受験地の法務局・地方法務局に受験番号が掲示
⇒法務省のホームページに合格者の受験番号が掲載
⇒合格者本人に筆記試験合格通知書(口述試験受験通知書)が郵送
Ⅰ 試験形式
各自、指定された時間に1人ずつ2人の試験官に口述で回答を求められます。
Ⅱ 試験科目
・不動産登記法
・商業登記法
・司法書士法
・司法書士の業務を行うに必要な一般常識
Ⅲ 所有時間
1人あたり15分程度
※よほどのことがない限り、口述試験(二次試験)で落とされることはないそうですので、実質的には、筆記試験(一次試験)さえ合格すれば、ほぼ司法書士試験合格と考えていいようです。
※仮に、「筆記試験」には合格し、「口述試験」で不合格だったとしても、翌年の「筆記試験」は免除になります。
⇒筆記試験の管轄法務局・地方法務局に掲示
⇒法務省のホームページに合格者の受験番号が掲載
⇒合格者の名前が官報に公示。 司法書士試験合格者証が交付
***PR・広告***
記述式について(不動産登記法・商業登記法)
司法書士業務を遂行するための「実体法」「手続法」についての『法的知識』の有無を問われる。
具体的には、ほとんどの問は5肢択一問題マークシート方式。
それら『法的知識』を使って、実際に法的問題を解決することができるか否かの『法的スキル』の有無を問われる。
具体的には、依頼人からの依頼内容や登記記録その他の書面を見て、読み解き『法的知識』を使って申請すべき「登記申請書」を作成する。さらには、不動産登記・商業登記各々約1時間以内に「登記申請書」を書き上げ、法的問題を解決できなければならない。
つまり、「総合問題」&「応用問題」としての位置づけのいわば、実技試験。
不動産登記法/記述式の概要
◆問題文の設定としては、例えば「司法書士の法務花子さん」が登場し、そこへ”「依頼人」が「必要書類」を持ってきて不動産登記に関する登記申請の代理を依頼する”というような設定になっています。
①現在の不動産の登記記録
②「各種契約書」「住民票」「戸籍謄本」「審判書」「領収書」「配達証明書」など、登記の現場で実際に扱われている書面(いわゆる別紙)
これらの①~③の書類を検討し、「不動産の登記記録」を最新のものに書き換えるための「申請書」を、ストーリー上登場する「司法書士」に成り代わり、作成していきます。
そして、その「作成すべき申請書」を「解答用紙」に書くという構成です。
また、ストーリー上登場する「依頼人」への「アドバイスやその理由」を解答したり「別パターンの依頼」が示され、「その申請ができるかできないか」を「その理由と共に解答せよ」というような問題文もあります。
◆不動産登記法/記述式で、かなり重要な部分とされているのが、申請の順序です。
商業登記法/記述式の概要
◆問題文の設定としては、ストーリー上登場する「とある会社の代表者」が「司法書士」のところへ「必要書類」を持ってきて商業登記に関する「書類作成」など登記申請の代理を依頼する”というような設定になっています。
①現在登記されている会社の登記記録
②「株主総会議事録」「取締役会議事録」「種類株主総会議事録」「定款の一部抜粋」「株主リスト」など
これらの①~③の書類を検討し、「会社の登記記録」を会社の決定にしたがって最新のものに書き換えるための「申請書」を、ストーリー上登場する「司法書士」に成り代わり、作成していきます。
そして、その「作成すべき申請書」を「解答用紙」に書くという構成です。
また、「必要書類」の中には、例えば「決議要件」をクリアーしていない等の適法でないものも含まれている場合もあるので、それを選別して除外する作業も必要となります。
このように、「記述式」とは「長文」を読み解き、「必要書類」からどのような登記申請が必要なのか?の判断を、”いかに速く・正確”に解答できるかを試されるもので、「実務的」な「即戦力」が要求される試験といえると思います。

以上、司法書士試験の概要でした。
***PR・広告***