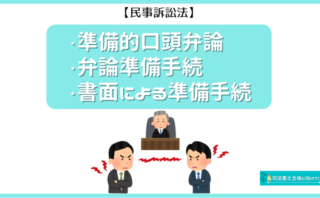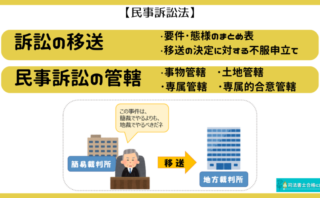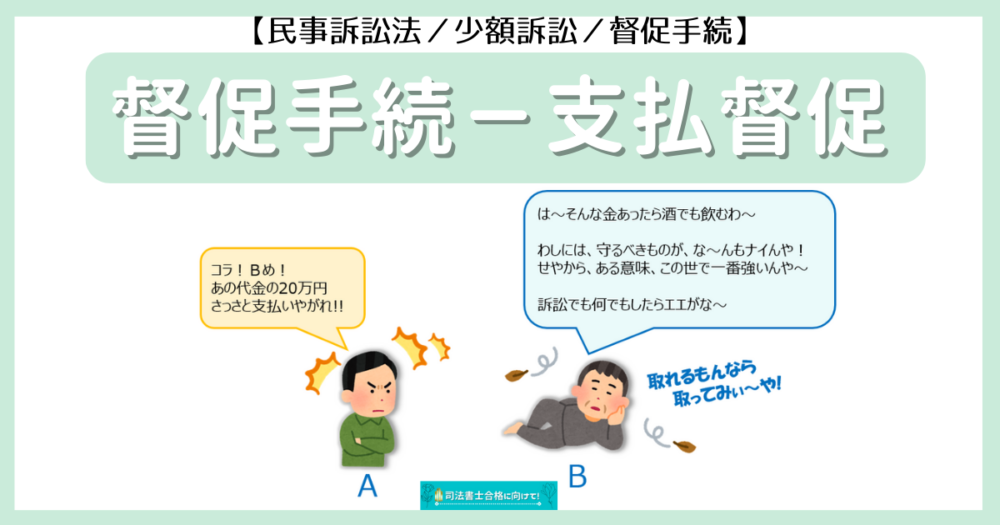今回の記事は、
01 略式訴訟手続とは?
a.簡易裁判所の訴訟手続
b.少額訴訟
c.督促手続(支払督促)
d.手形訴訟
e.少額訴訟・支払督促・手形訴訟の比較まとめ表
なお、「00 訴えの変更と反訴の比較」と「01 略式訴訟手続」は、別の章とはなりますが、メインの「01 略式訴訟手続」には、「反訴」が出てきます。
その関連で、「00 訴えの変更と反訴の比較」を加えました。
00 訴えの変更と反訴の比較


訴えの請求として、
b.被告側からの「反訴」
があります。この2つについて、比較しながらまとめています。
a.訴えの変更とは?
訴えの変更とは、原告がしていくことで、訴訟が係属中に、当初からの手続きを維持しながら、当初の審判対象を変更していくことです。
訴えの変更は2種類
訴えの変更には、次の2種類あります。
Ⅱ.旧請求と交換して、新たな請求を提起していく「訴えの交換的変更」
(※訴えの交換的変更は、「追加的変更」と「訴えの取下げ」の複合形態です。)
訴えの変更するための要件
「訴えの変更」をするためには、一定の要件を満たさなければなりません。
→ただし、請求の基礎に変更があるときでも「被告が同意したとき又は応訴したとき」は可です。
Ⅱ.著しく訴訟手続を遅滞させないこと
→たとえ被告が同意した場合でも、訴訟を著しく遅滞させることになる場合には訴えの変更は認められません。理由は、訴訟経済という公益的な見方をするからです。
Ⅲ.事実審の口頭弁論終結前であること
Ⅳ.交換的変更の場合には、相手方の同意があること
→交換的変更の中の「訴えの取下げ」部分について被告の同意が必要です。
b.反訴とは?
反訴とは、被告が原告に対して提起する訴えのことで、係属中の本訴の手続き内で、関連する請求について提起していきます。
反訴を提起するための要件
「反訴」をするためには、一定の要件を満たさなければなりません。
Ⅱ.事実審の口頭弁論終結前であること
Ⅲ.著しく訴訟手続を遅滞させないこと



「反訴」は、「訴えの変更」と比べて、要件はゆるいニャ。
「反訴」は、提起しやすいのニャ。
c.訴えの変更と反訴の比較まとめ表
「訴えの変更」と「反訴」の比較まとめが次のとおりです。
| 訴えの変更 | 反 訴 | |
| 主体 | 原告 | 被告 |
| 要件 | Ⅰ 請求の基礎に同一性があること ※提起し辛い・厳しい |
Ⅰ 本訴請求又はこれに対する防御方法に、関連すれば反訴提起はOK ※提起しやすい・ゆるい |
| Ⅱ.口頭弁論終結前であること | ||
| Ⅲ.著しく訴訟手続を遅滞させないこと | ||
| 相手方の同意 | 不要 (※交換的変更の場合は相手方の同意が必要) |
不要 (※控訴審においての反訴は相手方の同意が必要) |
***PR・広告***
01 略式訴訟手続
略式訴訟には、次の4種類があります。
b.少額訴訟
c.督促手続(支払督促)
d.手形訴訟
a.簡易裁判所の訴訟手続
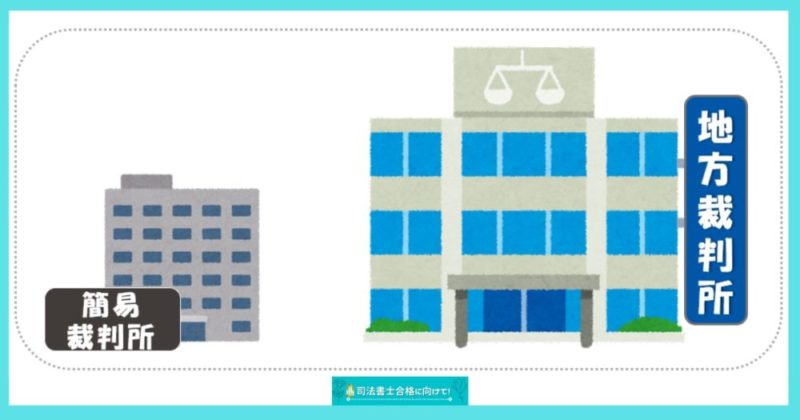
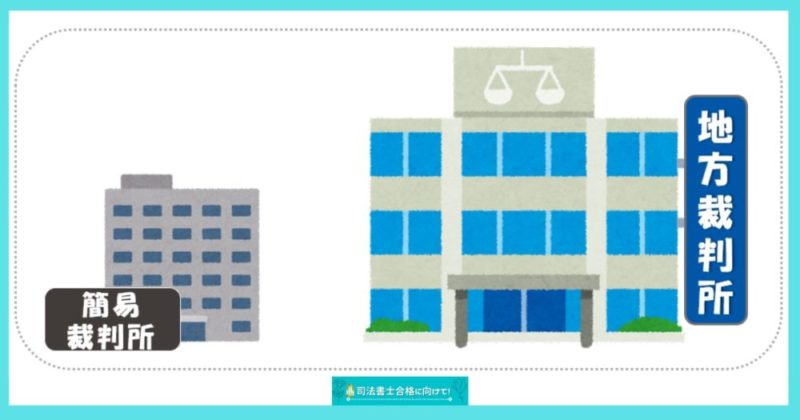
簡易裁判所の訴訟手続について、地方裁判所の訴訟手続と比較しつつまとめました。
| 簡易裁判所 | 地方裁判所 | |
| 管轄 | 訴額が140万円を超えない場合 | 訴額が140万円を超える場合 |
| 訴え提起の方式 | ・口頭による訴えもOK ・訴状提出 |
・訴状提出による訴えしかできない (口頭による訴えは不可) |
| 請求 | 請求の原因に代えて、紛争の要点を明らかにすればOK | 請求の趣旨,請求の原因を訴状に必ず記載しなければなりません |
| 陳述擬制 準備書面等の提出により、陳述したものと擬制することができます。 |
続行期日でも、陳述擬制が認められます | 最初の期日のみ、陳述擬制が認められ、続行期日には認められません。 |
| 司法委員 民間人が司法委員となり、和解の補助をしたり、意見を聴くことができる制度です。 |
民間人の司法委員の制度があります。 | なし |
| 尋問等に代わる書面の提出 | ・証人・当事者の尋問 ・鑑定人の意見の陳述 ・・・に代えて書面の提出ですませることができます。 |
原則:尋問方式に限る 例外:証人尋問の代えて、書面の提出をさせることが可能です。 |
***PR・広告***
b.少額訴訟
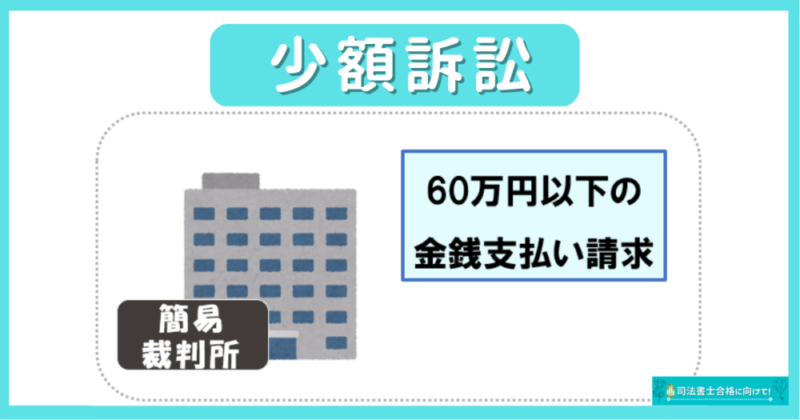
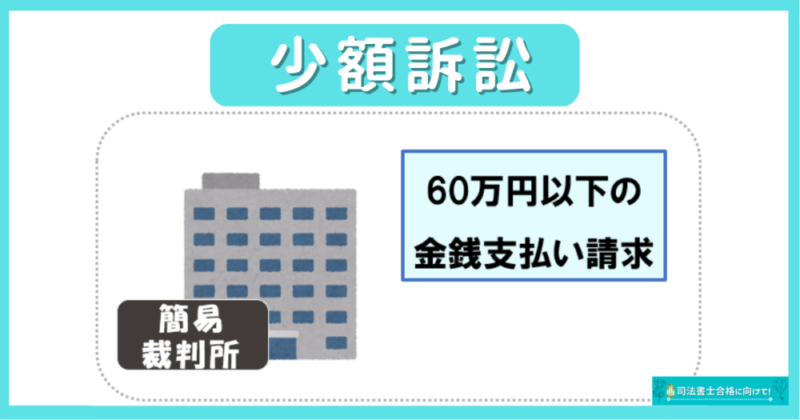
少額訴訟についてまとめた表が次のとおりです。
| 対象 | 60万円以下の金銭支払請求 |
| 管轄 | 簡易裁判所 |
| 回数の制限 | 同一の原告が、同一の簡易裁判所において、同一の年に『10回』まで利用することができます。 ※貸金業者等の反復利用をやめさせるためです。 |
| 被告からの通常訴訟への移行の申述制度 | ・少額訴訟を提起された場合に、被告としては、口頭弁論期日において「通常訴訟への移行の申述」をすれば、訴訟は「通常の訴訟手続」に移行することができます。 |
| 原告からの通常訴訟への移行の申述制度 | 原告からの申述制度は、ありません。 |
| 審理 証拠調べ |
【一期日審理の原則】 ・最初に開かれる口頭弁論期日前orその期日において、すべての攻撃防御方法を提出しなければなりません。 ・証拠調べは、即時に取り調べ可能なものに限定されています。 (※即時に取り調べができるのなら、証人尋問も可能です。) |
| 反訴 | 反訴提起は不可 |
| 支払猶予や 分割払いの可否 |
被告の資力等を考慮して、判決言渡日から3年を超えない範囲内で、支払猶予or分割での弁済等を命じることができます。 |
| 仮執行宣言 | 職権で「仮執行をすることができること」を宣言しなければなりません。 |
| 不服申立て |
【控訴】 少額訴訟の終局判決に対して、控訴することはできません。 【異議】 |
c.督促手続(支払督促)


②日本において、公示送達によらないで支払督促を発布することができること
③債務者を審尋しないこと
④管轄違いによる移送はできないこと(→この場合、却下になります。)
その他、督促手続(支払督促)について、ザックリまとめた表が次のとおりです。
| 対象 | ・金銭その他代替物 ・有価証券 |
| 管轄 | 簡易裁判所/書記官 |
| 証拠調べ | 証拠調べは、ナシ ※支払督促は、債務者を審理しないで発布されるので、証拠調べはなされません |



支払督促の請求の価額に制限はないのニャ。
つまり、140万円超でも、支払督促することは可能だニャ。
***PR・広告***
d.手形訴訟


手形訴訟についてまとめた表が次のとおりです。
| 対象 | ・手形による金銭の支払請求 ・それに付帯する賠償請求 |
| 管轄 | 訴額に応じる
訴額が140万円を超えない場合は、簡易裁判所 |
| 【土地管轄】 被告の住所地+手形の支払い地 |
|
| 審理 | 【一期日審理の原則】 ・訴えが提起されると、裁判長は直ちに口頭弁論期日を指定し、当事者を呼び出さなければなりません。 ・やむを得ない事由がない限り、最初に開かれる口頭弁論期日において、審理を完了しなければなりません。 |
| 証拠調べ | 【原則】 ・証拠調べは『書証』に限られます。 ・その『書証』は、挙証者の所持する文書に限られます。 →なので、✖文書提出命令 ✖文書送付嘱託 【例外】 →つまり、 |
| 反訴 | 反訴提起は不可 |
| 支払猶予や 分割払いの可否 |
支払猶予も分割払いも不可 |
| 仮執行宣言 | 職権で「仮執行をすることができること」を宣言しなければなりません。 |
| 通常訴訟への移行 | 原告から通常訴訟への移行が可能です。 (※被告の同意は、不要です。) |
***PR・広告***
e.少額訴訟・支払督促・手形訴訟の比較まとめ表
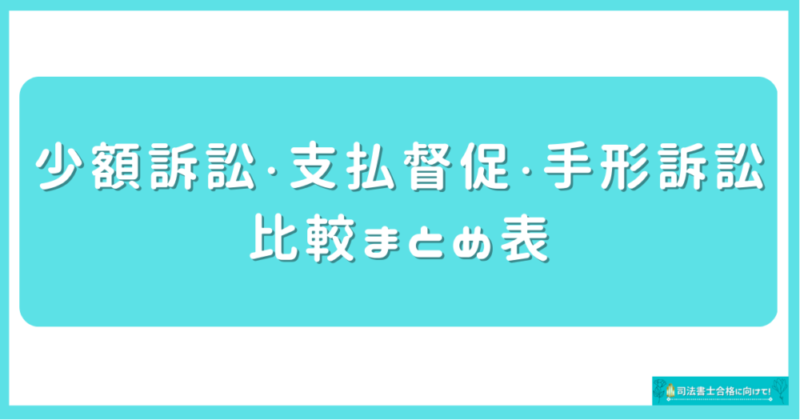
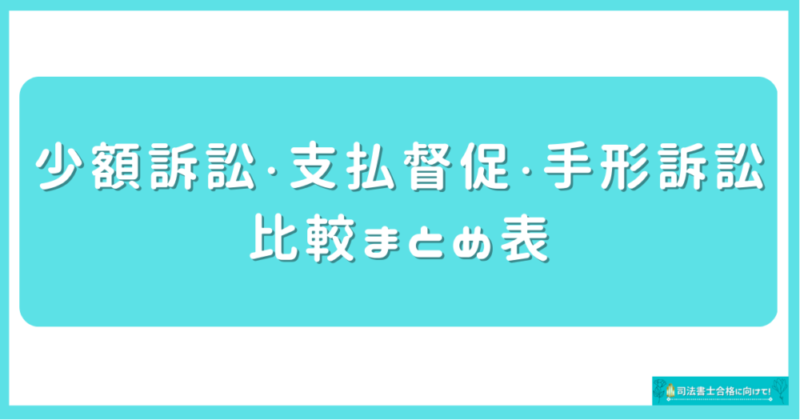
少額訴訟・支払督促・手形訴訟についてをザックリまとめた表が次のとおりです。
| 少額訴訟 | 支払督促 | 手形訴訟 | |
| 対象 | 60万円以下の金銭支払請求 (1年以内は10回まで) |
・金銭その他代替物 ・有価証券 |
・手形による金銭の支払請求 ・それに付帯する賠償請求 |
| 管轄 | 簡易裁判所 | 簡易裁判所/書記官 | 訴額に応じる
訴額が140万円を超えない場合は、簡易裁判所 |
| 証拠調べ等 の制限 |
・即時に取り調べ可能なものに限定 | 証拠調べは、ナシ | ・挙証者の所持する書証に限定
・「文書の成立の真否」 |
| 証人尋問の可否 | 即時に証人尋問できるなら可 | - | 証人尋問 不可 |
| 反訴提起 | 不可 | - | 不可 |
| 支払猶予や 分割払い |
支払猶予 可 分割払い 可 |
- | 不可 |
| 仮執行宣言 | 職権で「仮執行をすることができること」を宣言しなければなりません。 | ||
| その他 | ・控訴:不可 ・異議:判決をした簡易裁判所に対する異議の申立ては可 |
- | 原告から通常訴訟への移行が可 (※被告の同意は、不要) |
以上、訴えの変更と反訴提起,簡易裁判所と地方裁判所の比較,少額訴訟・支払督促・手形訴訟の比較まとめでした。お疲れ様でした。
***PR・広告***