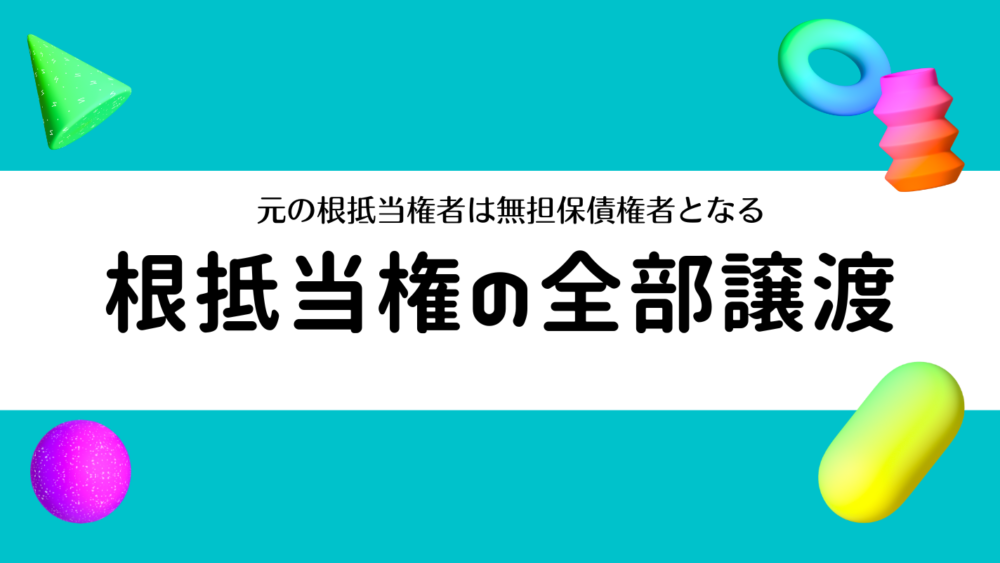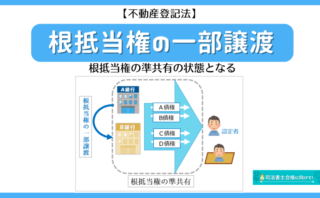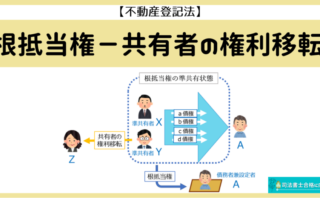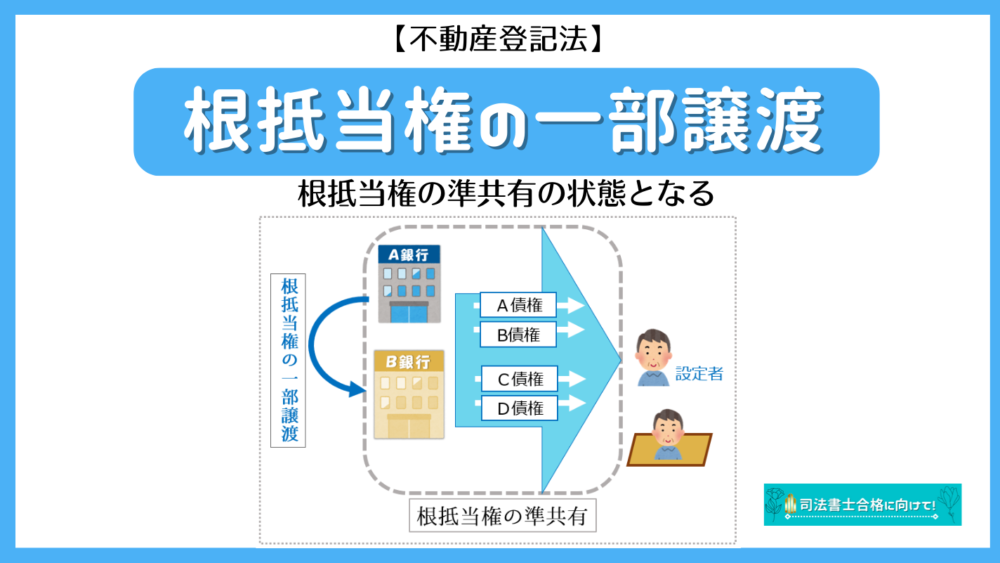このブログ記事に沿った動画を作成しました。是非、youtubeでご視聴下さい。よろしくお願いします。
根抵当権は、元本確定前のみ、全部譲渡,一部譲渡,分割譲渡をすることができます。
・根抵当権の全部譲渡
・根抵当権の一部譲渡
・根抵当権の分割譲渡
◆元本確定前にのみできる登記です
◆根抵当権を全部譲渡すると、「元の根抵当権者」は無担保債権者になります。
◆今後は「譲受人の新・根抵当権者」の債権が根抵当権で担保されることになります。
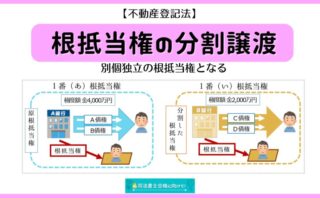
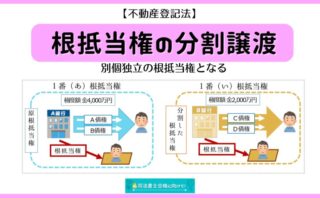
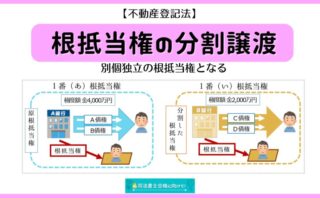
***PR・広告***
根抵当権の全部譲渡
【根抵当権の全部譲渡についての事例】
2.A銀行からB銀行に対し、根抵当権の全部譲渡をした。
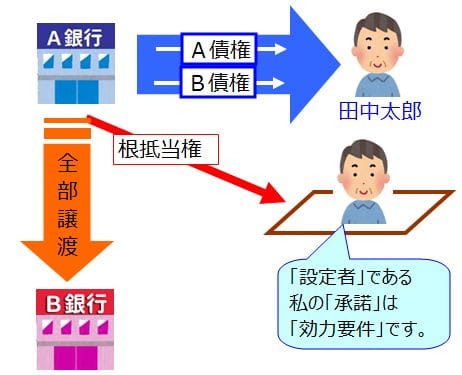
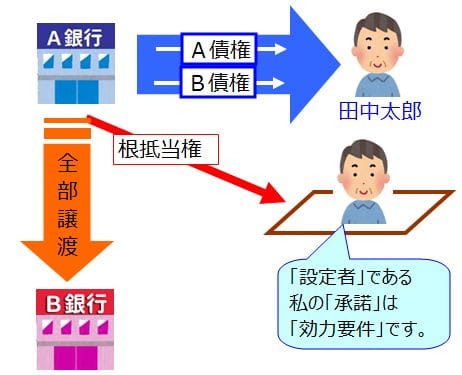
▼
4.今後は、B銀行の「これから取得する債権」「これまでに取得していた債権」「C債権・D債権」が担保されることになる。
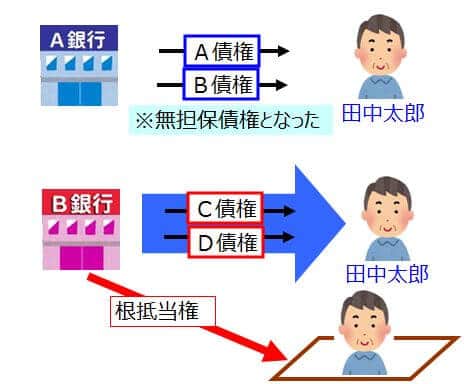
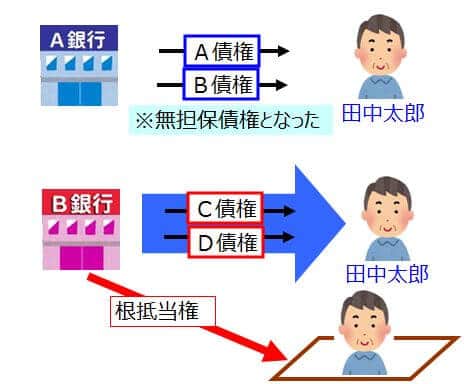
01 根抵当権の全部譲渡がされると、元々の「被担保債権」は無担保債権になります。
02 根抵当権の全部譲渡を受けた側(B銀行)は、
・これから取得する債権
・これまでに取得していた債権
・C債権・D債権
・・・が、根抵当権で担保されることになります。
***PR・広告***
利害関係人の承諾
根抵当権の全部譲渡での「設定者」としては、自分の不動産に根抵当権を設定していて、いつの間にか勝手に「根抵当権者」が変わっていたとなっては、なんとなく気が悪いです。
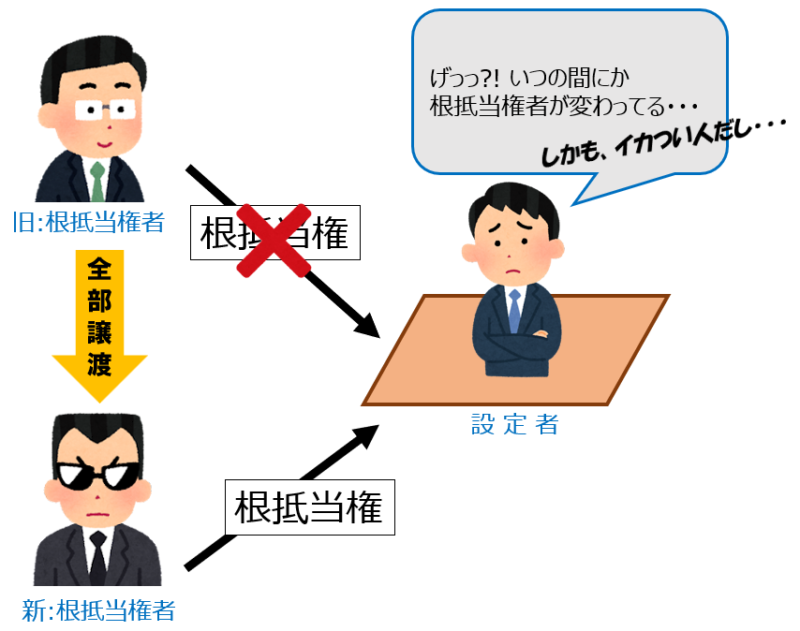
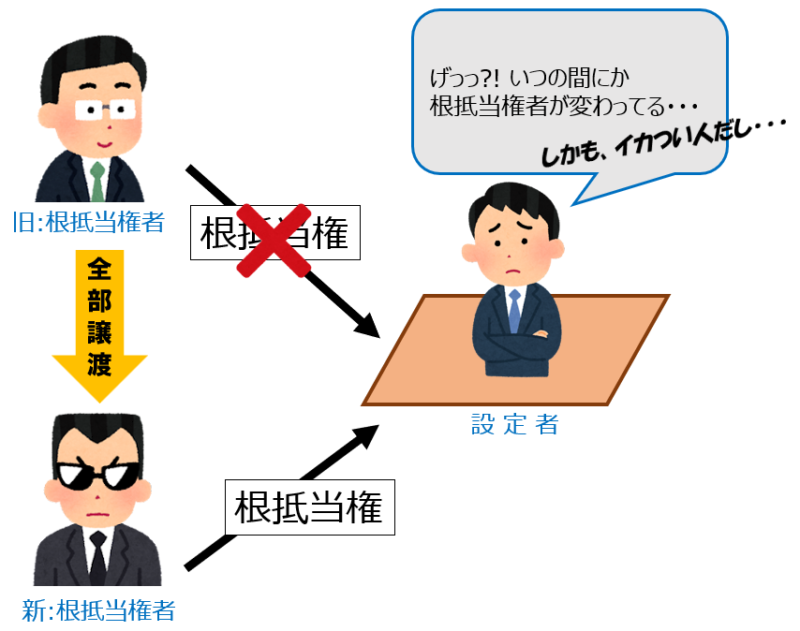
「効力要件」ということは、設定者の承諾を得られなければ、効力が発生しないということです。
→つまり、「契約日」と「設定者の承諾日」がずれていれば、原因日付は「設定者の承諾日」を書いていかなければなりません。
このように、「設定者の承諾」は、「日付に影響が出てくる」ことになります。
・「設定者の承諾」は原因日付に影響あり!
共同根抵当権の場合の登記について
共同根抵当権の場合には、全ての不動産に登記しなければ効力を生じません。
***PR・広告***
元本確定前
根抵当権の全部譲渡は元本確定前にしか、登記できません。
元本が確定した後には、登記できなくなります。
「根抵当権の全部譲渡」の効果としては、これまでのA銀行の「A債権・B債権」からB銀行の「C債権・D債権」が担保されることになるということから、「担保される債権」が変わってきます。
これは、つまり「債権の範囲」の変更と同じと捉えることができます。
そして「債権の範囲」は『根抵当権の3要素』なので、登記が効力要件です。
だから、「合意」と登記まで含めて「確定前」になされてなければならないわけです。
***PR・広告***
申請書の具体例
【事例】
②A銀行からB銀行に対し、根抵当権の全部譲渡をした。
③1番根抵当権が、A銀行からB銀行へ移転した。
| 登記の目的 | 1番 根抵当権 移転 |
| 原因・日付 | 令和○○年○月○日 譲渡 |
| 登記事項 | なし |
| 申請人の氏名 及び名称 |
権利者 (住所) 株式会社 B銀行 義務者 (住 所) |
| 添付情報 |
・登記原因証明情報 ・登記識別情報 ・承諾証明情報 ・会社法人等番号 ・代理権限証明情報 |
| 課税価格 |
金3000万円 |
| 登録免許税 | 金6万円 (←2/1000) |
原因日付
「合意の日」か「設定者の承諾」かいずれか遅い日を取っていきます。
⇒「設定者の承諾」が効力要件なので、「日付に影響が出てくる」ということです。
登記の実行
「所有権以外の移転」なので、『付記登記』で実行されます。
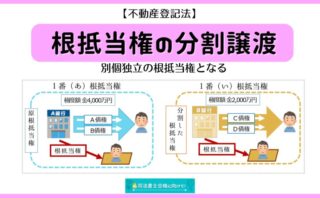
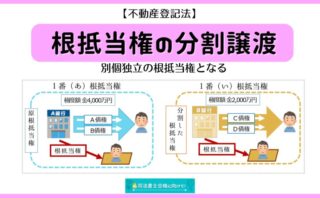
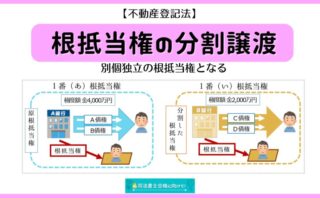
***PR・広告***